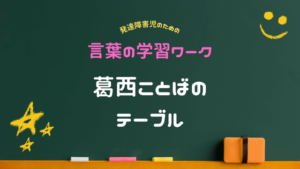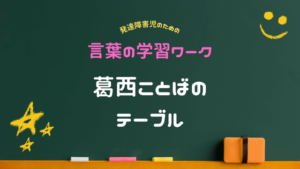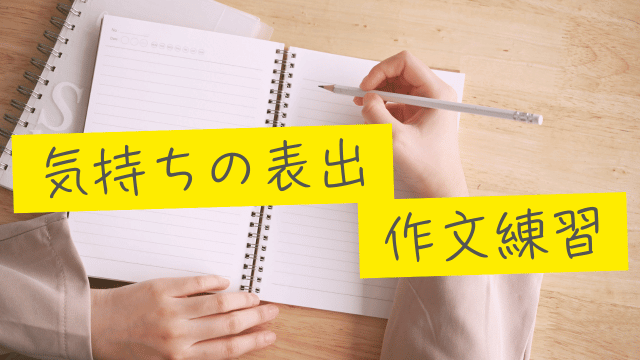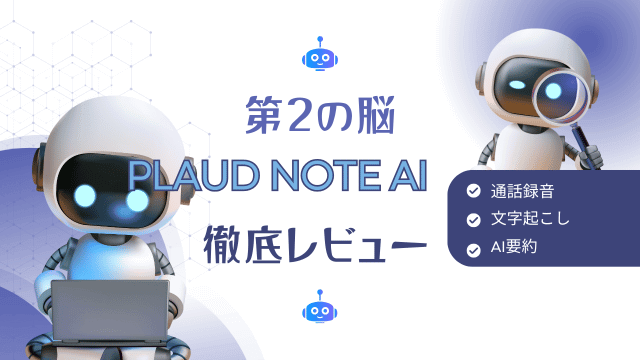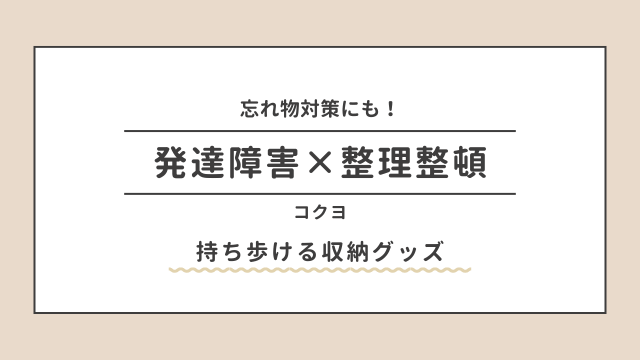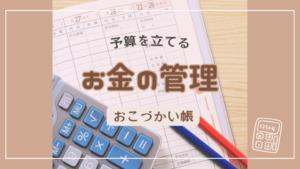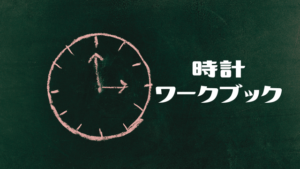発達障害のあるお子さんは、コミュニケーションの課題を抱えていて、自分の気持ちの表出が難しいことが多いと思います。
ある障害者の方が、お母さんが亡くなった後に、すぐに死を受け入れることができなかったけれど、自分の悲しい気持ちや、お母さんのとの思い出を毎日短い文章で表現していくことで、またそれを振り返ることで次第にお母さんの死を受け入れ、今は前向きに暮らしているというドキュメントを見ました。
気持ちを表現・アウトプットすることで人は、自己理解や内観が進み、気持が整理できるものだと考えています。
また、自分の気持ちは言えるのだけれど、言い方がキツかったり荒々しい感じが、大人になっても残る人もいます。
特に発達障害のある方は、視覚優位の特性があるため、頭の中で考えるよりも、文字や文章として適切に表現することが気持ちの整理として、一番あっている方法ではないかと私は思っています。
発達障害のある人の作文表現の練習としておすすめのワークブックをご紹介します。
ひとこと日記帳

特徴
ひとこと日記帳は、作文や日記を書くのが苦手な子のために、虹の子どもクリニック院長の河野先生が作られました。
先生によりますと、日本語は作文や日記を書く場合、時系列に書いていき最後に「楽しかったです」と感想・気持ちを書く流れになりますが、なかなか気持ちにたどり着けないことが、苦手意識を生むためにのひとつと考えられています。
ひとこと日記は、感情を最初に書く方法です。振り返りの時間に取り入れると効果です。
人の記憶の想起に大切なのは、感情です。その感情から辿って文章を作成していく。それを毎日、ひとことひとこと積み重ねて練習していく。
引用元:トラビコひとこと日記帳
毎日の保護者の皆さんや先生方からのコメント、そして、シール、ご褒美チケットの活用でさらにモチベーションがあがるというものです。
- どんなことがありましたか?〇をつけてみましょう
- 先に気持ちを選択
- それはいつのことですか?
- それはどこでありましたか?
- だれと一緒でしたか?
- 何がありましか?
- つなげてみましょう
- まとめてみましょう
⑥と⑦の違いは、⑥は1から5をそのままつなげて書き、⑦はつなげた文章を読んでみて、違和感があったところを順序を入れ替えたり、接続詞を入れたりしてまとめて書くようにします。
ことばのテーブル
ことばのテーブルは言語聴覚士である三好純太さんが、クリニックの学習教室で実際に使われているワークを、教室だけでなく、広く活用してもらえればという思いで作られたものです。
作文練習ワーク
その中の作文練習ワークでは、1文から2~3文単位までの、作文能力を育成するものです・
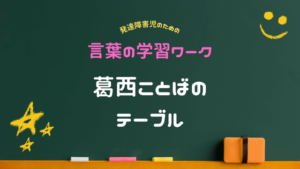
グレーゾーンの子どもに対応した作文ワーク
「グレーゾーンの子どもに対応した」シリーズは算数版もあり、2004年に出た古いものですが、初級編と上級編とあります。以前は中級編もあったのですが、今は販売されていないようです。今でも人気があるワークです。
ゆっくりていねいに学びたい子のための作文ワーク
「ゆっくりていねいに学びたい子のための」シリーズは、全部で12冊のワークが出ています。こちらも2017年発売の古いワークですが、今でも人気があり口コミも評価が高いです。
小学1年生から論理的に書ける「三文作文」練習帳
こちらは発達障害児向けではないのですが、名門附属小学校で教鞭を取り、全国各地で教師向けの勉強会を主催している先生の作文ノウハウを家庭学習用に集約したものです。
ステップアップ式なので、どんな子でも無理なく取り組める作文練習帳の決定版です。
目次
はじめに
本書の使い方
- 第1章 1年生レベル 三文作文を書く
- レッスン1 Aおおまかの文 Bくわしくの文 Cきもちの文
- レッスン2 きもちの文を「思ったこと」(心内語)にかえる
- レッスン3 くわしくの文を「二文」以上にふやす
- 第2章 2年生レベル 「くわしくの文」を工夫する
- レッスン4 くわしくの文に「会話文」を入れる
- レッスン5 くわしくの文に「音のことば」(ぎ声語)を入れる
- レッスン6 くわしくの文に「様子のことば」(ぎたい語)を入れる
- 第3章 3年生レベル 「書き出し」を工夫する
- レッスン7 書き出しを「会話文」にする
- レッスン8 書き出しを「ぎ声語」で書く
- レッスン9 書き出しを「ぎたい語」で書く
- 第4章 4年生レベル 「気持ちの文」を工夫する
- レッスン10 気持ちの文を「行動描写」の文に直す
- レッスン11 気持ちの文を「情景描写」の文に直す
- 第5章 読書感想文を書く
- レッスン1 「三文作文」方式で、読書感想文も書ける
- レッスン2 読書感想文のいいところは?
- レッスン3 三種類の文に書く内容をたしかめよう
- レッスン4 自分の心が動いた本を選ぼう
- レッスン5 A大まかの文 本の選んだ理由を書こう
- レッスン6 Bくわしくの文(前半) 本のあらすじを書こう
- レッスン7 Bくわしくの文(後半)一番よかったところとその理由を書こう
- レッスン8 C気持ちの文 自分がこれからしたいことを書こう
- レッスン9 これまで書いたことを清書しよう
- 読書感想文の書き方(まとめ)
娘の場合
娘は知的障害と自閉症を持っていて、小さいころはほどんど話すことができませんでした。
言語訓練にも通っていても、言葉を理解しているようだけど、自分からの主張・表現がされることはほぼありませんでした。
そんな娘も今は、毎晩今日あったことを日記にして書いています。こうゆう時間をあえて作らないと、娘は自分の気持ちをあまり表現してくれないため、私が娘を理解するためにもとても役立っています。
色々なワークをやって文章が書けるようになったので、今は「小学生の生活日記」に今日の出来事や気持ちを書いて振り返っています。

2025年版で3年目に入りました
娘はこういうノートがある方がいいみたいですね
その内、スマホのアプリなどデジタルに移行できればと考えています