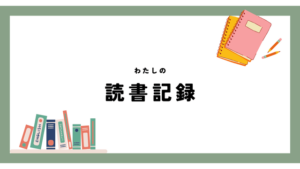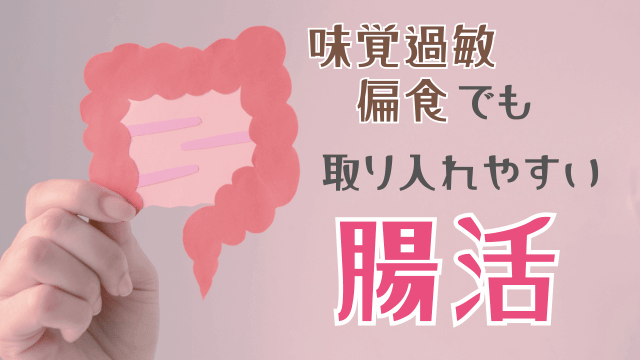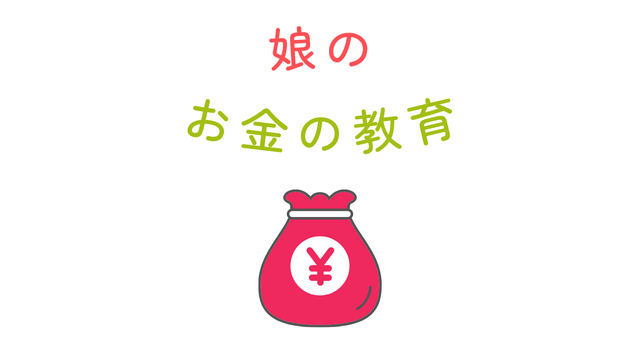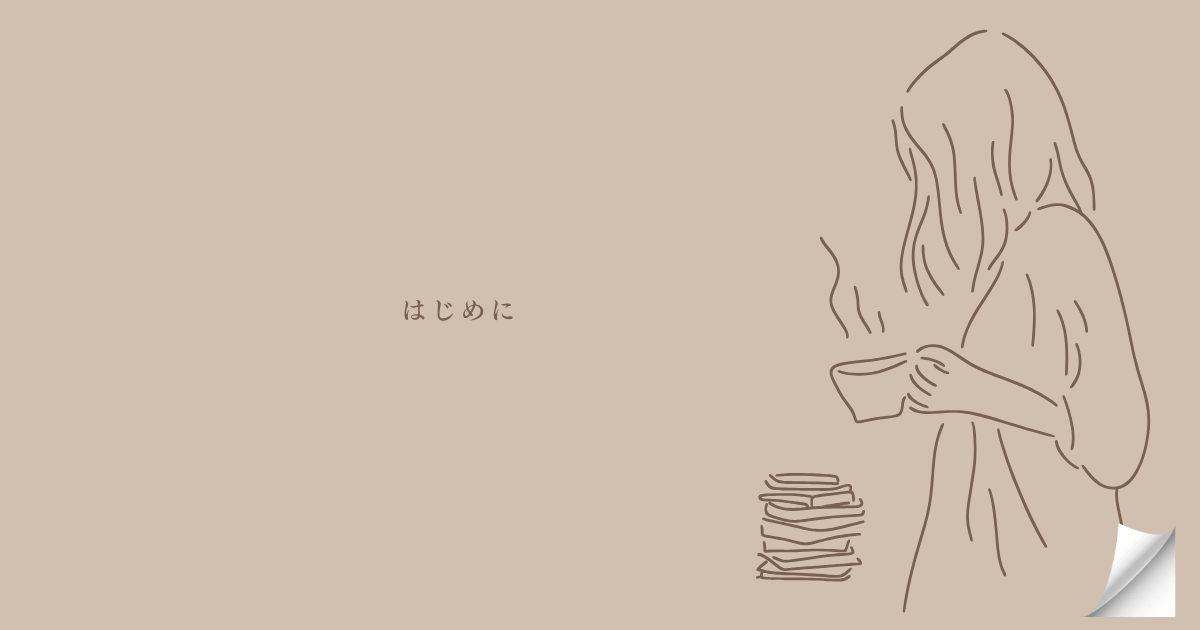
当ブログにお越しいただきありがとうございます☆とても嬉しいです(^^)
注意点
冒頭から恐縮ですが、当ブロクの【注意点】について先に説明させてください。
100人いたら100通り
「発達障害は100人いたら100通り」と言われる障害です。
そのため私が今まで多くの本を読み、情報を集め「試行錯誤」を繰り返した経験を元に書かせていただきましたが、それはあくまで一個人の主観に基づいたものです。
100通りなのですから、そもそも全員に合う対策・方法・正解は存在しません。
私のやり方が、あなたのお子さんに必ず合うとも思っていません。
例えば視覚支援をおすすめしていますが、視覚支援が合わないお子さんも知っています。
なので多くの情報から試行錯誤してあなたのお子さんに合った方法を探して欲しい。
その情報の1つとして私の情報が役に立つことがあればとても嬉しく思います。
その点をご理解いただいて読んでいただければ幸いです(*‘∀‘)
PDCAサイクル
先ほど試行錯誤といいましたが、強度行動障害の研修では、Plan(計画)・Do(実行)・Check(評価)・Act(改善)の順にサイクルを回すPDCAサイクルを推奨しています。
参考:強度行動障害支援者養成研修強度行動障害のある人の「暮らし」を支える
PDCAサイクルは、仕事でよく使われる用語ですが、強度行動障害者だけでなくても、子育てにも使えますし、PDCAサイクルを知らなくても、自然と行ってる親御さんもたくさんいると思います。
最近では、Observe(観察)、Orient(方向づけ)、Decide(意思決定)、Act(行動)のOODAループの方が、変化に強く自由度が高いからいいとも言われていますが、どうなのでしょう。
どちらにしても、発達障害の子育てには試行錯誤をし続けることが大事だと考えています。
知的障害児と勉強について
当ブログでは、勉強のワークブックなどをご紹介していますが、お子さんに「勉強を勧めている」わけではありません。
知的障害者が勉強できても、就労に有利に働くことはありません。
それよりも毎日を穏やかに暮らすことの方が大事です。
じゃあなぜ勉強のことを書くかというと、ある程度の読み書き計算ができると本人の生活が楽になるからです。勉強とは本来自分のためのものです。
娘に文字を教えたことで、コミュニケーションが取りやすくなり深い話もできるようになったし、数がわかることで、時計が読めるようになって時間配分や予定が分かるようになったり、計算や数学的な考え方は日常生活のあらゆる場面で使うことができます。
勉強できない場合
では逆に、娘が「勉強できない子だったら、どうしていたか」考えてみると、勉強を教えることはしなかったと思います。
その代わり、時間はタイムタイマーを使い、コミュニケーションはタブレットを使ったり、道具を使って少しでも本人が楽に生活できる方法を模索し続けたと思います。
新しいことを教えるに工夫が必要で最初は大変ですが、本人が楽になるということは、後々親も楽になるということだと思っています。

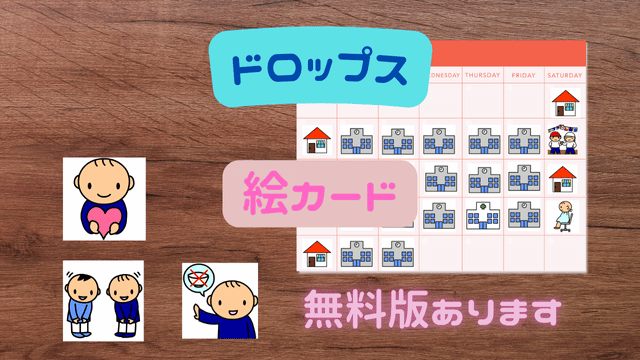
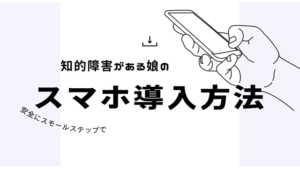
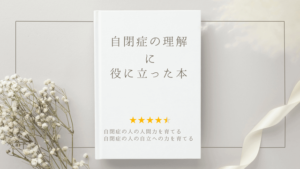
幅広い方に情報をお届けしたい
当ブログにお越しくださるかたは、何らかの形で障害者に関わる方だと思っております。
内閣府 障害者白書R5年度版によると、障害3区分の割合は、人口1000人あたりにすると身体障害34人・精神障害49人・知的障害9人となるそうです。
娘は知的障害と自閉症がありますが、人口の少ない知的障害向けの情報だけでなく、発達障害向けの情報も広くお届けした方が、どなたかの役に立つと思っています。
その点もご理解いただき、当ブログを活用していただければと考えております。