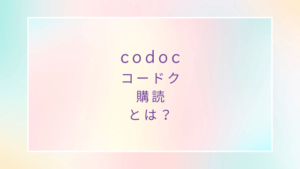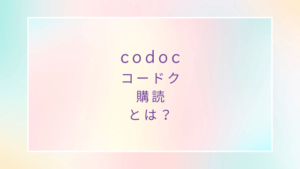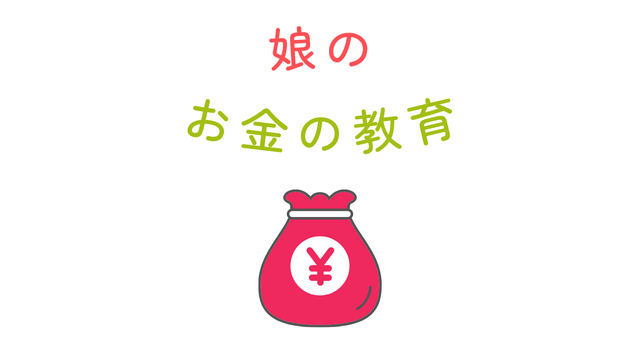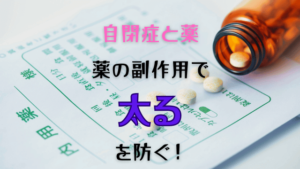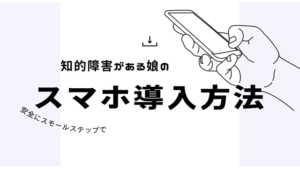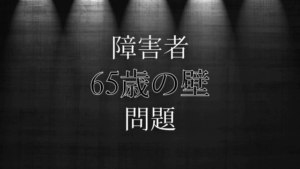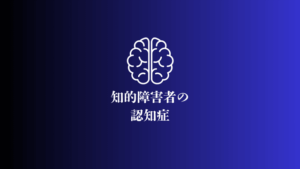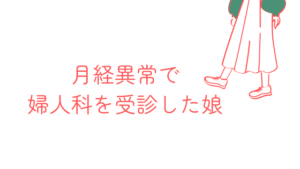日本はお金の教育が遅れていると言われています。
親自身が、お金の教育を受けてきていないということも原因ですが、日本独特の嫌儲思想も影響しているとも言われています。
また当たり前ですが「計算ができること」と「お金の管理ができる」のは別のことです。
娘は計算が得意で、お金の支払いもできますが、お金を渡すとあるだけ使ってしまう子でした。また小さい時はATMから、いくらでもお金が出てくると考えていました。
親亡き後は、後見人にお金を管理してもらうことになりますが、自分に渡されたお金は上手に使い生活を楽しんで欲しいと思い、小学2年生からお金の教育を始めました。
今では自分で考えてお金を使えていますが、それはたくさん失敗を経験し、それに対し試行錯誤した結果から学んだことです。
金銭感覚は一朝一夕には身につかないと実感しています。
特に知的障害がある娘は、お金の管理をパターン化し習慣化したことで、本人も迷わずに管理できるようになりました。今回は障害児のお金の管理について書いていきます。
日本ではタブー視されるお金の話
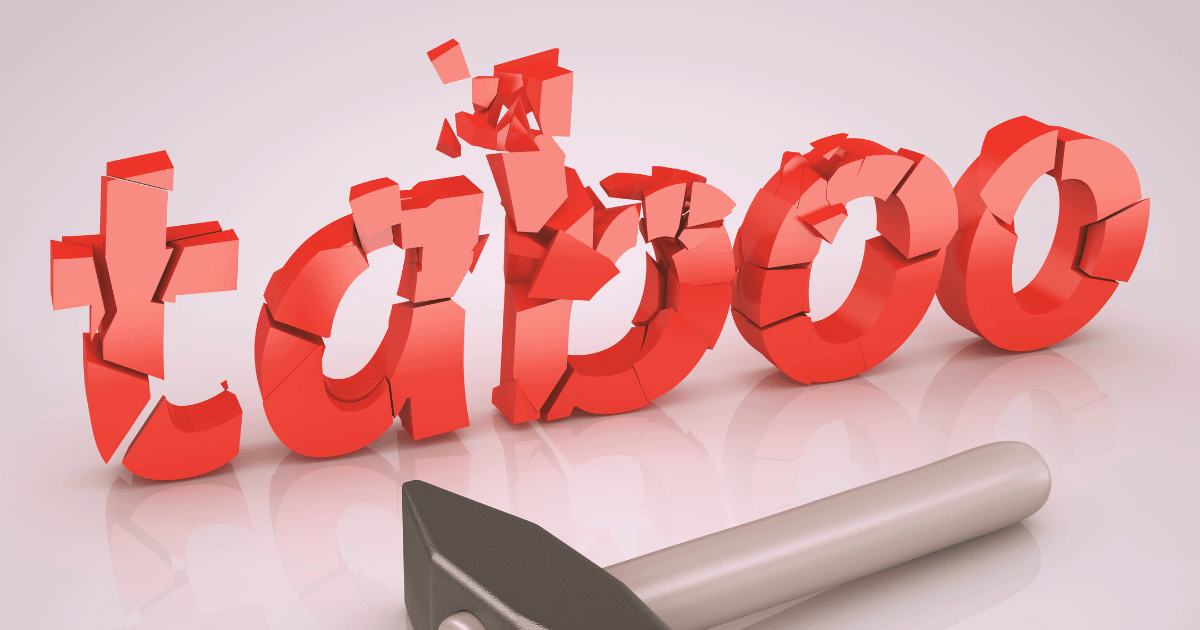
日本では、人前でお金の話をするのは「はしたない」「下品」という価値観がありますよね。
清貧・質素倹約・つつましいという言葉もあり、貧しさが美しい、正義という考えの人もいて、貧しい中苦労して生活している人は立派な人と考える人もいます。
節約や倹約はいいことだと思いますが、中にはその考えが行き過ぎて、大金を稼ぐ人は悪いことやズルをしていると考える人もいます。
「嫌儲思想」とは、このように他人が利益を得る事や成功することに対して否定的な感情を抱く考え方や態度を嫌うことをいいます。不労所得なんてダメという人もいますよね。

コロナ禍に仕事先の方が、ネットで稼ぐ人のことを「今の時代に稼いでる奴は悪いことしてる奴に決まっている」と言っていました
新しいことが受け入れられない人はいますね。どんな職種であろうと、稼ぐ人が増えると日本経済が回って豊かになり、税金を払う人が増え、福祉にお金が入るのにと思いながら聞いていました。
歴史的背景
しかし実は、日本人が「お金は汚いもの」と考えるようになったルーツは江戸時代にあるという話もあります。
士族生まれの原は、「金もうけは卑しい」と言われて育てられました。しかし、「その考え方は権力者の思う壺だ」と言う龍五郎。
もともと江戸時代が300年も続いたのは、国民が豊かになれないよう、巧妙に仕組み化されていたことにあります。参勤交代によって大名は資金を蓄えることができず、お金を扱う商人は卑しい身分と見なされました。
(略)
今の日本人にとって、蓄財法がもっぱら貯金一辺倒になったのも、「第二次大戦前に、国が戦費調達の原資として貯金を推奨したこと」や、「戦後の高度成長期には、定期預金に高い利息が付いたこと」などが大いに関係しているでしょう。
このように、私たちの価値観や考え方は、気づかないうちに過去から続いている慣習や政策の影響を受けています。
引用元:リクナビ 日本人は、なぜ「お金の話」をするのは恥ずべきことだと思うようになったのか?
インベスターZの話ですが私も好きなマンガです。
嫌儲思想は、作られたメンタルノイズ(思考や行動を妨げる心のクセ)と言われています。小さい時に周りにそういう大人が多ければノイズは強く、もはや刷り込まれて洗脳されている状態ともいえます。



アインシュタインの「自分の常識は他人の非常識」という言葉もありますよね
特にお金に関しては、親の思想を受け継いでいる人が多いように感じます。親が生きている間に「相続の話をするなんて不謹慎」という人もいますよね。
日本でもお金の教育がはじまる
アメリカの公教育では、基本的な金融教育は小学校低学年(5~7歳)から始まり、中学校からより実践的な授業が行われています。
日本でお金に関する教育が本格的に議論されるようになったのは、2000年代以降です。
小中学校では2020年以降、学習指導要領の改訂により、「消費者教育」や「生活設計」の重要としてお金に関することを学び、高校では2022年度から新設された科目である「公共」と、従来からある家庭科の中の「家庭基礎」または「家庭総合」で学習指導要領改訂で盛り込まれました。
今後は終身雇用制もなくなり退職金も期待できなくなり、年金だけでは生きていけない時代になる。さらに増税は続き、誰もが先行き不安な時代に突入しました。
お金の教育とは
ChatGPT にお金の教育について尋ねてみると次のような答えが返ってきました。
お金の教育とは、お金の使い方や管理方法、価値について学ぶことです。
具体的には、以下のような内容が含まれます。
- お金の基本的な仕組み
- お金の役割や種類、稼ぐための仕組みを理解する。
- 予算管理と計画性
- 収入と支出のバランスをとる方法や、将来のための貯蓄を
- 価値観と消費の選択
- 必要なものと欲しいものを区別し、賢い消費
- 投資や資産運用
- お金を増やす方法やリスクについて学び、長期的な視点で資産を考える力を身につける。
- 金銭トラブルの回避
- 借金や詐欺を恐れる知識を持つ。
お金の教育は子どもから大人まで重要で、日常生活をより豊かにし、経済的な安心感を得るための基盤になります。
お金の教育と一口にいっても、教えることはたくさんあります。
子どもの成長や能力に合わせて教えていきたいです。



今後を生きる子ども達に、お金の教育は必要不可欠です
学校の授業だけでいいのか
お金は日常生活に必要な道具です。学校で一律に教育を受けても、本当の理解には実践が必要ですし、失敗もたくさんして学んでいくものだと思っています。
特に発達障害や知的障害がある場合、その子の理解度を把握して、その子の能力にあわせて、親が丁寧に教えていくのが一番だと私は考えています。
学校の先生は一生懸命やってくれますが、当たり前ですが期間が定められているし、あなたの子どもは全体を通しての1人にしか過ぎません。過度に期待せず、子どもを一番理解している親が教えた方がいいと私は思っています。
お金のワークブック


今はお金の支払いや計算については、ワークブックが多く出ています。
幼児向けや障害児向けのワークブックは、視覚的にとても分かりやすく、お金シールもついていますので、発達障害や知的障害がある子でも、楽しみながら学ぶことができておすすめです。





娘もワークブックを通してお金を学びました
得意不得意
娘は知的障害がありますが計算が得意で、簡単なものだと暗算もできます。お金の支払いも一人でできますし、お小遣い帳もつけています。
娘に数学的なセンスがあるのは、父親からの遺伝で持って生まれたものなのか、または計算の脳領域だけ損傷していないのかも知れません。教えるのに視覚的な工夫は必要でしたが、割と苦労せずにスポンジのように吸収していきました。
以前、知り合いのお母さんが「知的障害があっても勉強できる子はいて、その中でも算数が得意な子・国語が得意な子にわかれるように思う」と言っていました。国語と算数の二択かは不明ですが、確かに娘は国語が苦手なので、知的障害であっても理系脳/文系脳があるのかも知れません。
そのお母さんのお子さんは支援級在籍で、小学校入学前に既に掛け算ができていたそうです。
また勉強以外では、支援学校で重度知的障害があっても、家族の分の料理を作れる子やピアノが弾ける子もいます。お母さんに教えたのか聞くと「好きでやっているんだよね」というから、娘と同じく得意なことを伸ばすのに労力はあまりかからないということなのでしょう。
知的障害児と勉強について(私見)
勉強ができると書くと、私が「勉強を勧めている親」と誤解される方もいるかも知れませんが、そんなことはありません。勉強できない子に勉強させるのは反対です。
知的障害者が勉強できても、就労に有利に働くことはありません。それよりも毎日を穏やかに暮らすことの方が大事です。
じゃあ何故勉強のことを書くかというと、ある程度の読み書き計算ができると本人の生活が楽になるからです。勉強とは本来自分のためのものです。
娘に文字を教えたことで、コミュニケーションが取りやすくなり深い話もできるようになり、数がわかることで、時計が読めるようになって時間配分や予定が分かるようになり、計算や数学的な考え方は日常生活のあらゆる場面で使うことができます。
幸せな人生とは何か
勉強できない子に勉強させるのは反対と書きました。何故そう考えるのか。
ノーベル経済学賞を受賞したジェームズ・ヘックマン教授によると、人間の総合能力は
- 認知能力【学力・IQ・記憶力】と、
- 非認知能力【社交性・協調性・やり抜く力・自制心・思いやり・信頼・自尊心・勤勉性】
とに分けられ、(数値化しやすい)認知能力が高いからといって幸せな人生をおくる因果関係は全くみられず、逆に非認知能力が高いと判断された子は、幸せな人生を送っていることが証明されたのです。
※日本生涯学習総合研究所の分類では、非認知能力は【批判的思考力・実行・統率力・創造性・自己肯定感・共感性・道徳心・倫理観・問題解決力・協働力・コミュニケーション力・主体性・自己管理能力・探求心・規範意識・公共性・独自性】を示す。
更に非認知能力が高い子は、その能力により周囲からの適切な手助けを受けやすく、結果的に勉強ができるようになり、経済的にも成功しやすいことが分かっています。
今後、総雇用の47%の仕事が自動化されるといわれています。AIに置き換えられる認知能力よりも、人間は非認知能力を育てて、好きなこと得意なこと向いていることを伸ばしてあげることの方が、幸せな人生をおくれるのではないでしょうか。
例え知的障害や発達障害があっても、非認知能力が高いと思われるお子さんはいて、先生や周りの支援者、同じ障害児から好かれている、頼りにされいる子が多いです(娘もそういう子たちが好きです)。障害があったとしても、そういう子が幸せな人生をおくるのだと私は思っています。
勉強できない場合
では逆に、娘が「勉強できない子だったら、どうしていたか」考えてみると、勉強を教えることはしませんでした。無理に教えても自己肯定感が下がるだけです。人には得意不得意があります。
その代わりに、時間はタイムタイマーを使ったり、コミュニケーションはタブレットを使ったりして、道具を使い少しでも本人が楽に生活できる方法を模索し続けたと思います。
新しいことを教えるに工夫が必要で最初は大変ですが、本人が楽になるということは、後々親も楽になるということだと思っています。


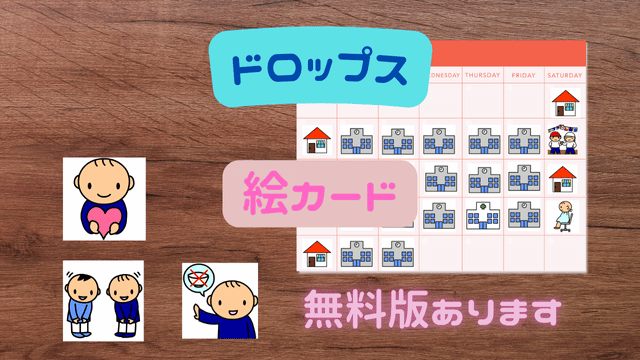
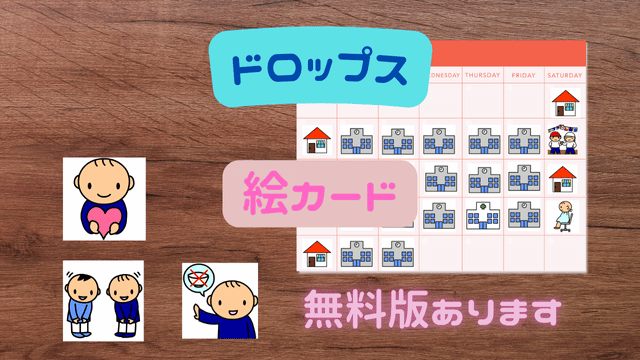
お金の教育の本
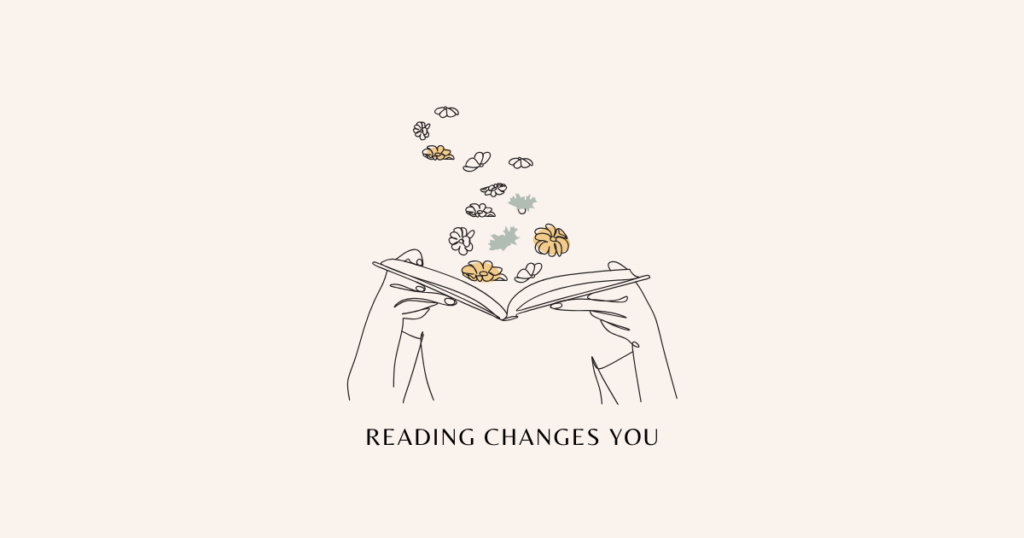
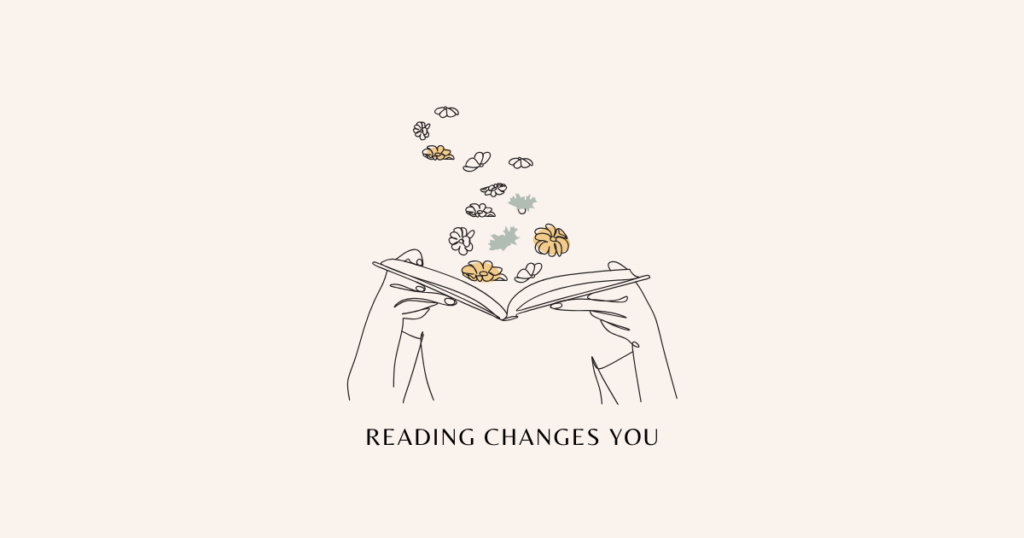
将来を見据え、お金の教育をはじめました。
娘だけではなく、私自身のためにも多くのお金の情報や本を読んできました。私は本を読み、多くの情報をインプットすることで、娘に試してみたいアイデアが出てきます(点と点の情報がつながって線になるイメージです)。その知識のおかげで、娘のお金の教育も上手くいっています。
お金の教育関連の本を読み始めたのは2015年、娘が小学2年生からになります。
以前はこのような本はあまり出ていませんでしたが、最近はたくさん出ていますね。障害とは関係のない本ですが、勉強になったり面白い本もたくさんあります。皆さんも興味があれば是非読んでみてください。



知的障害のないお子さんなら、漫画版など子供向けに読みやすいものも多く出ています



①~④の本は今ならkindleで無料で読めます
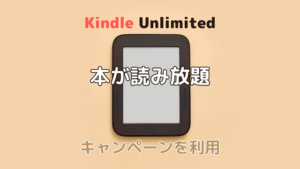
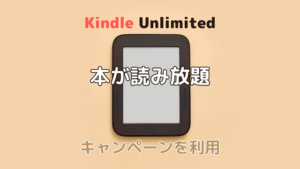
障害児には工夫が必要
本を読んでも知的障害がある娘には、そのままのやり方は通用しませんから、分かりやすいように工夫して教えていきました。
知的障害がある場合は、自分で考えて管理することは上手くいきませんから、親が考えたものが子どもにあうかを試行錯誤で試していき習慣化、パターン化して日常に落とし込むことを年単位で行うのが一番上手くいくと実感しています。
今回はそのことを書いていきたいと思います。



今は無料の情報が多くありますが、本当に有益な情報はお金を払わないと手に入らないと思っています。私の情報がお役に立てると嬉しいです。