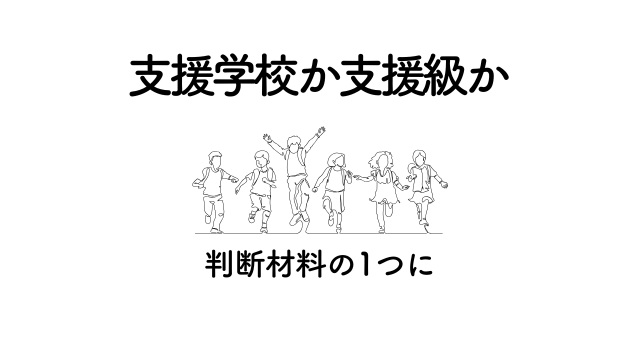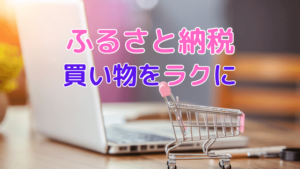小学校入学前の就学相談で(知的障害の)支援学校【判定】を受けたものの、実際に支援学校を見学して「本当にここでいいのか」と迷ったことはありませんか?
特に中度知的障害があるお子さんの場合、「全部ができないわけじゃない」「集団の中でもある程度やっていけそう」という場合も多く、親として判断がとても難しくなります。
私自身、娘の就学前に支援学級と支援学校の両方を見学し、支援学校を選びました。
支援学級は、地域の小学校に通えることから、兄弟や近所の子と一緒に登校し、学校行事にも参加できるなど、「普通の小学生らしい生活」がイメージしやすい場所です。そして支援学級を選ぶのは、「できることを少しでも増やしてあげたい」という親の前向きな想いが込められています。
一方で支援学校の授業は、一見するとバラバラに見えたり、遊びのように思えたりして、短時間の見学ではその学習の意味や積み重ねの大切さまでは見えてこないこともあるのではないでしょうか。
また、途中から支援学級から支援学校へ、転校してくるお子さんもいます。小学校高学年になると増える傾向があり、環境の違いに戸惑って適応に時間がかかることもあります。そうした様子を見るたびに、「最初の進路選びが本当に難しい」と感じます。
この記事では、娘が支援学校に通った経験に加えて、他の保護者の声や学校の先生、医師、福祉サービスの方、セミナーで聞いた話などをもとに、「支援学校」と「支援学級」の実情についてまとめています。
進路選びに迷っている方の参考になれば幸いです。
この記事で扱う主なテーマ
- 「特別支援教育」について
- 支援学校に通うなら知っておきたい14のポイント
- 支援学級を選ぶ前に押さえておきたい5つの視点
- 「支援学級→支援学校」へ──転校で起こる4つの課題
- 「小・中学部」の知的障害の特別支援学校について書いています
- 知的障害に加えて発達障害を併せ持つお子さんを想定した内容が中心です
- 地域やお子さんの状態によって状況が異なる場合があります
あわせて読みたい

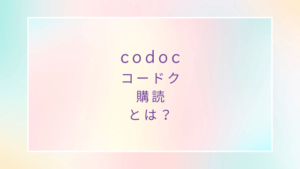
codoc(コードク)について
このサイトでは有料記事については、codoc(コードク)という販売ツールを使用しています。 コードクとは、WEBサイト上でコンテンツ販売を可能にするための、決済機能を…